9月28日の「国際セーフアボーションデー」を記念し、9月25日(水)にウェビナー「経口中絶薬の導入から1年経過、今起きていること」が開催されました。本イベントは、「セーフアボーション(安全な中絶・流産)」のテーマにそれぞれの立場から取り組む産婦人科医を中心としたメンバーで構成されるリプラ(リプロダクティブライツ情報発信チーム)と公益財団法人ジョイセフの共催、IPPF(国際家族計画連盟)の後援で行われました。
国際セーフアボーションデー(International Safe Abortion Day)には、「安全でアクセス可能な中絶」の認知度を上げるため、世界各国で様々なアクションやキャンペーンが行われています。
本ウェビナーには、医療関係者だけでなく、幅広い層から100名以上の参加がありました。
ウェビナーの中では、まずジョイセフから
「安全な中絶とは何か」を日本の中絶の歴史を振り返りながらの説明がされました。

リプラからは、二人の産婦人科専門医にご登壇いただきました。一人目の柴田綾子さんからは、経口中絶薬導入後の日本の状況、緊急避妊薬と人工妊娠中絶薬の違いや、中絶手術後の合併症、薬剤を用いた中絶の安全性について、さらにWHO中絶ケアガイドラインエグゼクティブサマリーの内容を元に、世界と日本の経口中絶薬の使用方法の違い、日本の導入の遅れについての説明がありました。

二人目の空野すみれさんからは、安全な中絶が必要な理由、薬剤による中絶のメリット、e-Learning教材の説明がされました。
この教材は、IPPFとWomen First Digital (WFD)が制作した『How To Use Abortion Pill』(リプラと日本助産学会が翻訳)という動画です。「当事者を中心としたケア」「権利に基づくケア」「質の高いケア」「プライバシーと守秘義務」という4つの原理原則を守り、国際産婦人科連合(FIGO)によって承認されています。日本でも最新の調査研究に基づき、少しでも多くの人に中絶の安全性と正しい使用方法への理解を促していくことを、本教材を通して目指しています。
動画もご覧いただけますので、詳細についてはこちらの記事をご参照ください。
中絶は女性の心と身体を守る手段の1つであり、WHOは「中絶の制限や規制」を撤廃することを提唱しています。近年の調査によると、遠隔診療と対面診療では特に初期では副作用に大きな違いが見られなかったとの報告があり、安全性も確認されています。
厚生労働省によると2023年時点で日本の人工妊娠中絶方法は、掻爬(そうは)法の単独が約1割、掻爬法と吸引法の併用が約2割となっています。
WHOは、掻爬法は時代遅れの外科的手術であり、合併症の観点から行うべきでないと勧告し、2020年には、掻爬法は訓練を受けた人が施術したとしても安全性が低い、と発表しましています。
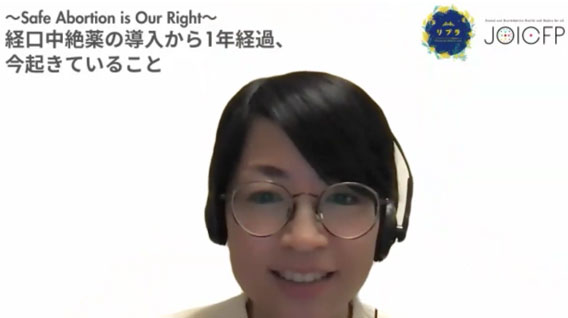
ウェビナーの後半では「中絶前後のケア」について取り上げられました。WHOは妊娠12週までの中絶において自己管理の選択肢を推奨しています。中絶を行う当時者が意思決定者として中絶を行うにあたり、セルフケアに必要な支援として情報の提供、薬の提供、心理的な支援などが紹介されました。
本ウェビナーや教材の動画等を通じて、中絶の正しい知識が広まり、多くの人に理解されることで、より安全で効果的な医療が提供される日本社会の実現を願います。
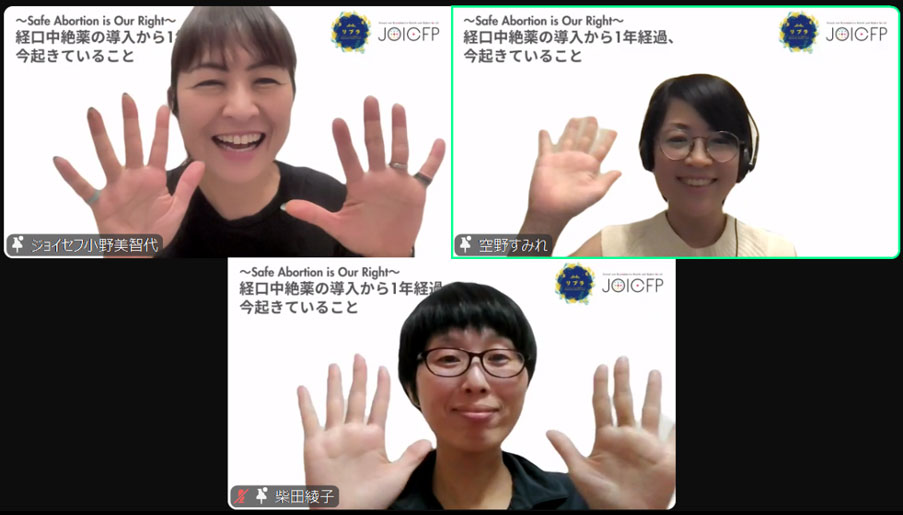
when
country
日本








