
ジェンダーの平等は基本的な人権です。貧困を撲滅し未来の世代の人生をよりよくするために必要不可欠です。ジェンダーの平等は、私たちのすべてのプログラムと政策提言活動の中心にあります。IPPFは、女性性器切除(FGM)や早期強制結婚、またその他のジェンダー差別と戦うために、法的また政治的な変革を推進します。
Articles by ジェンダーの平等
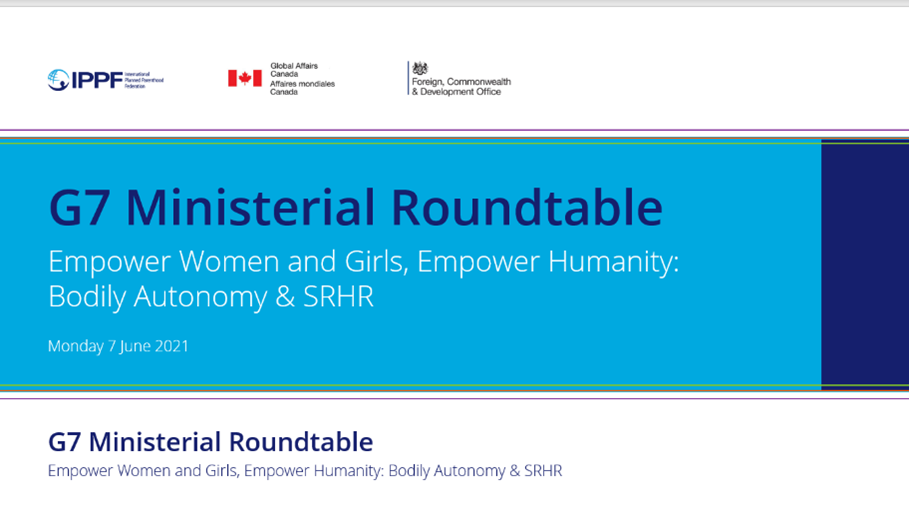
IPPF・G7ハイレベルラウンドテーブル:G7各国がUHCの実現に喫緊のSRHRへの取り組み強化を表明
IPPFは、11日から英国で開催されるG7サミット直前の6月7日、オンライン会合G7ハイレベルラウンドテーブル「女性と少女に力を、全ての人々に力を:身体の自己決定権とセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)」(以下、ハイレベル会合)を英国・カナダ両政府と共同開催しました。 5月3-5日に英国で開催されたG7外務・開発大臣会合で、G7外務・開発大臣は共同コミュニケを発表し、包括的なSRHRサ ービスへの普遍的なアクセスが、人々の命を救い、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する上で 極めて重要と認識した上で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行がSRHRに及ぼす深刻な影響への対処と防止、SRHRの普遍的な実現に向けた進展を加速していくため、G7以外の国々や市民社会との連携を含めた、SRHRへの取り組み強化にコミットしました。 ポストコロナ社会をより良く、より公平なものにするためには、SRHRを社会の中心に据えなくてはなりません。SRHRは健康のみならず、ジェンダー平等の実現にも重要な役割を担っているからです。 このハイレベル会合の大きな目的は、G7・ゲスト国の高官が、前述のコミュニケに含まれたSRHRへの取り組み強化のコミットメントを果たす重要性について話し合い、この機運を11日から英国で開かれるG7サミット、30日からフランスで開催される「平等を目指す全ての世代フォーラム(Generation Equality Forum)」につなげることでした。ハイレベル会合にはG7・ゲスト国の9カ国(米国、英国、インド、オーストラリア、カナダ、ドイツ、日本、フランス、南アフリカ)より4名の大臣を含む政府高官が参加しました。日本政府からは、小野啓一外務省地球規模課題審議官が出席し、以下のように述べました。 「COVID-19は、脆弱な人々の窮状を悪化させました。最も弱い立場にある人々に最初に手を差し伸べることは、UHCを実現するためにも、また、SRHRを含むCOVID-19に対する効果的なジェンダー対応を確保するためにも重要です」 他の政府高官からは「パンデミックの影響で学校に戻れない何百万人の若者向けに質の高いエビデンスに基づいた教育が欠かせない」、「パンデミックへの対応と、女性と少女のニーズへの対応とを統合できるような、より良い保健システムの構築が必要」などの発言がありました。 ハイレベル会合後、IPPF事務局長のアルバロ・ベルメホは次のように話しました。 「日本政府代表の小野地球規模課題審議官を含むG7ハイレベルラウンドテーブル参加者から受けたSRHRへの力強いコミットメントに大いに勇気づけられました。COVID-19が、人々(特に女性や少女などの脆弱な人々)の健康と生活に大きな影響を及ぼし、健康格差が広がり続けています。G7・ゲスト各国の首脳が、G7外務・開発大臣会合コミュニケで明言した、SRHRの普遍的な実現に向けた取り組み強化のコミットメントを、確実に実行していくことを強く望みます」

ジェンダーに基づく暴力はあまりにも多い―しかし予防はできる
国際家族計画連盟(IPPF)グローバル・リード、ジェンダー・インクルージョン セリ・ウェンドー 世界中で、女性の3人に1人が生涯のうちに暴力を受けています。つまり、7億3,600万人の女性が親密なパートナーか、またはそうでない人から身体的、精神的、性的な暴力に遭います。過去10年間、この数字はほとんど変わっていません。女性と少女に対する暴力が私たちの社会の中でどれほど当たり前のものとして存在し、毎日、誰かが暴力を受けているのだと思うと、恐怖を感じます。 女性が親密なパートナーから暴力を受け始めるのは、驚くほど早くからです。15-19歳の少女の1/4近く(24%)が身体的暴力か性的暴力、またはその両方を親密なパートナーから受けたことがあります。 上記の数字はすべて最近、発表された女性に対する暴力に関する世界保健機関(WHO、2000-2008年)の 報告書にあります。報告書に書かれた事実はどれも許しがたいものです。私たち全員の問題として考えなければなりません。 女性に対する暴力は、何より個人の人権の侵害であり、グローバルな保健医療の危機ですが、「『社会的・文化的規範』によって有形無形に規定される」と考えられます。暴力は身体・性的・精神的暴力など様々な形態があります。例えば、職場か公共の場におけるセクシュアル・ハラスメント、女性性器切除(FGM)、強制的に早婚させられ、結果としてスティグマ(社会的な汚名)を受けること、などです。 新型コロナウイルス感染症とジェンダーに基づく暴力 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大以前にも、低所得国と中低所得国では、多くの女性が暴力を受けていました。世界中で見ても、女性に対する暴力が著しく増加しています。女性の多くは、暴力をふるう相手とロックダウン中に自宅で過ごさざるを得ず、必要な医療ケアを受けられませんでした。 IPPFのCOVID-19タスクフォースが加盟協会(MA)に実施した数回の調査結果から、親密なパートナーによる暴力と、加害者とロックダウン中に過ごした女性が受けるドメスティック・バイオレンス(DV)の件数が増えたことが明らかになっています。さらに、身を守るための情報と教育を受ける機会が奪われ、特に若者たちに悪影響があったことも分かっています。 少女たちのセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)を害する慣習の撤廃を目指す活動によって得られていた一定の成果がパンデミックのために後退し、性暴力を受け、結婚を強制され、退学する少女の割合が増えました。 コロナ感染拡大前と比べ、若者たちは避妊法と安全な中絶、抗レトロウイルス薬、性感染症治療などのケアを、大幅に受けにくくなりました。ロックダウン、外出禁止、感染防止のための隔離に隠された状態でFGMが増えていないか、懸念が増します。 多くのMAは、オンラインで包括的性教育(CSE)やカウンセリングを実施するなど、デジタル機器を通じてサービスを提供する手段を模索してきました。しかしデジタル格差(スマートフォン、コンピュータ、インターネット接続が使えるかどうかの格差)のため、低所得国、中低所得国に住む思春期の少女たちには利用できません。 コロナ禍によってもっとも影響を受けたのは女性と少女であると確信を持って言えます。女性と少女の権利を前進させるために何年も続けてきた努力が無になったからです。今、急いでニーズに応えなければ、女性と少女たちは取り残されてしまいます。 暴力を受けた女性は、暴力の有無を医療従事者に伝えるかどうかは別として、暴力を受けていない女性よりも保健サービスを利用する確率が高くなります。その点において、医療従事者は暴力を受けた女性に対応する第一線の支援者です。だからこそ、最初に女性たちに接触する医療従事者に研修を行い、効果的で女性の視点に立った保健医療サービスを提供できる体制を作ることが肝要です。暴力を受けた女性には、もっとも質の高い医療ケアを受ける権利があります。 女性に対する暴力は予防できる IPPFのジェンダー・インクルージョンのグローバル・リードとして、女性に対する暴力は防止できると知っています。IPPFの素晴らしいMAがコミュニティで行う活動を見て、いつか女性と少女に対する暴力を根絶できるという希望がわいてきます。 IPPFマラウイ(FPAM)がコミュニティの指導者とソーシャルワーカーたちからなる監視グループの活動を通じて、効果的に児童婚を防いでいます。マラウイは強制早婚の割合が高く、少女たちの47%は18歳までに結婚しているという推計があります。 IPPFパレスチナ(PFPPA)は性暴力に関する啓発ワークショップ を実施し、地域の宗教指導者、その他のパートナーと連携して活動することで、人々にセクシュアル・ヘルス/ライツの情報を広めています。 インドのMAは、刑務所に入っている女性たちの出所後の生活準備を支援し、エンパワーメント しています。IPPFメキシコ(MEXFAM)の調査では、教師に包括的性教育(CSE)の知識があると、暴力を減らす必要性への学生の理解が高まることが分かりました。IPPFパキスタンは、スワート渓谷など各地で暴力防止のための活動を続けています。 これらは、人生を180度変えるようなMAの活動のほんの数例です。 活動を止めず、何とかしてジェンダー平等を実現するために、政治家、援助国などの決定権を持つ人々と機関に対し、これまでと同様、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)分野への拠出を続ける決意を求め、呼びかけます。医療従事者へのSRHR専門研修を支援し、マルチセクターなアプローチから女性と少女に対する暴力に対応し、CSEに投資してください。 今ほど、女性と少女への確固たるコミットメントが必要な時はありません。彼女たちの命がかかっています。 ※マラウィとインドでの活動はIPPF日本信託基金(JTF)プロジェクトとして始められました。また、IPPFパキスタンの取り組みの一部もJTFによって支えられています。

COVID-19関連:日本政府がセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ促進を要請する共同声明に賛同
5月6日、59か国が賛同する「COVID-19危機下においてセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツを擁護しジェンダーに基づいた対策の促進を求める」共同プレス声明が発表されました。日本政府も賛同国に加わっています。 共同声明は、主に以下の点を主張しています。 COVID-19が女性と男性に与える影響は異なる 女性と少女に対する暴力を防止するための特別な措置を導入しなければならない 緊急支援によって、難民、移民、国内避難民であるすべての女性と少女が守られるべき 社会心理学的な支援サービスを含むセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス(SRH)ニーズ、ジェンダーに基づく暴力(GBV)からの保護を優先する 学校が休校となる中、思春期の保健、権利、福祉を保障するため、社会的保護の責任を政府が負わなければならない すべてのレベルにおける意志決定への女性と少女の積極的な参加とリーダーシップの発揮を支援する ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の文脈において、セクシュアル・ヘルス(SRH)サービスは不可欠 セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)への資金提供を優先事項として残すことで、妊産婦と新生児死亡、避妊のアンメットニーズ(充足されていないニーズ)、安全でない中絶、性感染症の増大を避けなければならない 助産師、看護師、コミュニティヘルスワーカーの活動には個人防護服・防護具(PPE)が欠かせない 妊婦の呼吸器疾患、特にCOVID-19感染症は、悪化のリスクが高まるため、優先的に治療しなければならない 生殖可能年齢にあるすべての女性と少女に必要なリプロダクティブ・ヘルス関連の物資を提供することを約束する 特に脆弱な国々への緊急支援への参加と、保健医療ケアへのユニバーサルなアクセスを実現するというグローバルなコミットメントが完全な効果を持つための支援を要請 声明のPDFと詳細についてIはPPF東京連絡事務所であるジョイセフのページをご参照ください。 ※写真はIPPFバングラデシュ(FPAB)のコミュニティヘルスワーカーがCOVID-19下、SRHサービスを提供する様子です。

性的指向、性自認、性表現を差別的に扱う法律を変えるための新規プロジェクトを12カ国で開始
世界中に今なお根強く存在する多くの差別と偏見がありますが、その一つが個人の性的志向、性自認、性表現(SOGIE)に向けられたものです。 国際家族計画連盟(IPPF)は、すべての人々がいかなる差別も受けることなく、自分の健康(ウェルビーイング)や性について自由に決められる社会を目指しています。 その一環として、2019年11月、ナイロビでIPPFは性的指向、性自認、性表現(SOGIE)に関するIPPFの政策と啓発方針を策定するための会合を開きました。IPPFの各地域から加盟協会2団体、計12の加盟協会が参加しました。 参加者はそれぞれの国の政治状況を共有し、SOGIEに制限を課す法令をどのように変えるか、考えられる可能性と戦略について話し合いました。 幅広い啓発の経験と発想、課題を機会とらえなおすような創造的なソリューション、そしてこれまで勝ち取った成果の数々からインスピレーションを得たと、会議の参加者からフィードバックがありました。 SOGIEの権利については、世界中で様々な改善が行われてきましたが、190カ国のうち70カ国ではまだ、(性的マイノリティを)罰する法令があります。 司法制度を使って性的マイノリティの非刑罰化を実現するプロセスについてが、中心的な議題になりました。インド、ボツワナ、トリニダード・トバゴの加盟協会の代表がそれぞれの国でどのようにその戦略が成功したかを説明し、それを推進するのが性的マイノリティのためだけの活動をしているのではない保健・人権団体が活動する意義を話しました。 LGBTI団体との協働の例についても、団体の立ち上がりから活動初期にかけて支援する方法などが共有されました。時間をかけてパートナー団体とのネットワークを構築し強化することで、スキルと信頼を積み上げていけたという声が、いくつかの加盟協会から上がりました。 また、SOGIEの知識と対応能力をもった団体として啓発活動をしていく重要性と組織の強化についての議論に時間を割きました。インターンの活用と理事会組織にSOGIEへの理解とスキルがあることなどの対応例が共有されました。 国連の普遍的・定期的レビュー(UPR)のような国際的人権メカニズムは私たちのような団体にとって、シャドーレポートや現場の状況を伝えることで広く啓発活動ができる機会となります。さらに、世論に働きかける方法を説明するプレゼンテーション、必要な変化への認知度を上げるための方法、運動を作り上げる方法が紹介され、エビデンス(科学的根拠)とデータ収集の重要性が指摘されました。 これらの活動には資金が必要です。参加者は援助を求めるときに使えるアドボカシー計画を作りました。これらの計画はIPPF戦略に則って作られ、参加者はIPPFのツールを使ってどのように活動するかを話し合いました。 会合のまとめとして、これから公開されるイブラヒム・ムルサル監督の映画『ジ・アート・オブ・シン(The Art of Sin 原罪の芸術)』(IPPFノルウェー(Sex og Politikk)との共同制作)を見ました。スーダンで初めてカミングアウトした男性同性愛者の映画です。アフメッド・ウマールという芸術家が同性愛者としてカミングアウトし、スーダン(男性と性行為をする男性に対する死刑がある)とノルウェーで自分のアイデンティティを探求する姿を追います。 参加者 12のIPPF加盟協会(MA)が6つの地域から2人ずつ参加しました。チュニジア(ATSR)、モロッコ(AMPF)、ボツワナ(BOFWA)、ケニア(FHOK)、インド(FPAI)、スリランカ(FPASL)、北マケドニア(HERA)、ルーマニア(SECS)、カンボジア(RHAC)、インドネシア(PKBI)、ガイアナ(GRPA)、トリニダード・トバゴ(FPATT)この他IPPFの運営委員会と事務局が加わりました。 IPPF運営委員会には、アフリカ、アラブ、欧州、東・東南アジア・大洋州、南アジア、西半球の6つの地域から一人ずつ代表が参加しています。 このプロジェクトの事務局は IPPFノルウェー(Sex og Politikk)が担当します。
IPPFテクニカル・ブリーフ:セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖の健康と権利:SRHR)の新定義
この文書は、グットマッハー・ランセット コミッションが2018年5月に発表した報告書に基づいて、人権の観点からエビデンスに基づいた、包括的なセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖の健康と権利:SRHR)の新しい定義と、推奨される必須SRHR関連事業の包括的なパッケージについて、1ページにまとめました。

WHO事務局長 ジェンダー平等と女性の健康の大切さを訴える~UHCフォーラムサイドイベント 100人超が来場~
国際家族計画連盟(IPPF)は、国連人口基金(UNFPA)と、IPPF東京連絡事務所であるジョイセフ(JOICFP)とともに、2017年12月15日、「UHCフォーラム2017」公式サイドイベント「UHCとユニバーサル・リプロダクティブ・ヘルス・カバレッジ~女性・若者が直面する課題に挑む~」を東京都内で開きました。 約40ある公式サイドイベントのなかでも、セクシュアル・リプロダクティブヘルス/ライツ(SRHR)の視点はユニークで、WHO(世界保健機関)事務局長、国際保健を推進する日本の国会議員などがスピーカーとなり、約100人が参加する大規模なサイドイベントとなりました。 第1部では、大局的な観点から、UHC達成に必要なリーダーシップ、各国の実情に合わせた施策、そしてその時に女性の視点を取り込む大切さが述べられました。 基調講演をしたWHO事務局長テドロス・アダノム氏は、「誰一人取り残さない」ために、ジェンダー平等とSRHRは中心課題として取り組まないといけないことを強調しました。参議院議員の武見敬三氏は、日本のUHCの課題からみえる今後の問題点を説明し、高齢化社会のなか、非感染性疾患の増加、高齢女性の貧困、介護人材不足への対応の必要性を指摘しました。外務省国際協力局参事官の塚田玉樹氏は、世界の女性の地位向上とともに、SRHの大切さ、それに向けた日本の貢献を訴えました。 IPPF次期事務局長Dr アルバロ・ベルメホは、世界中の多くの人々、特に若者や貧困層は、SRHサービスを自己資金で利用することが多いため、自己負担を減らすよう、UHCを国の保健財政だけの問題とせず、「誰一人取り残さない」サービス供給の観点から考える必要があるとしました。 このほか、UNFPAテクニカル・スペシャリストのハワード・フリードマン氏、「女性と子どもの健康の実現に向けたグローバル戦略(Every Woman Every Child)」国連事務局アカウンタビリティー確保のための独立パネル代表のエリザベス・メーソン氏も登壇し、若者に特化したサービスやデータ収集の大切さなどを述べました。 第2部では、コミュニティの視点にテーマを移し、各地で抱える問題や若者の立場を考慮しながら、住民主体のサービスによる、UHC達成を議論しました。匿名で質問を投稿できるウェブサイトも利用し、若者を含めて活発な意見交換が展開されました。 IPPF アフリカ地域事務局長ルシアン・クアク氏は、米国のメキシコシティ政策によって若者の避妊具へのアクセスの障害が出たことを問題視するとともに、人工妊娠中絶に対して厳しい国があること、政情不安によって学校に行けない若者もいるなどアフリカが抱える課題を挙げ、政治の力、計画、活動、人材、実績が求められることを訴えました。 スーダン家族計画協会(SFPA)会長バシル・エリマム氏は、スーダンでは国内避難民のSRHの問題が深刻で、さらに各地で治安不安、貧困、地方部でヘルスサービス利用しにくいなどの問題を指摘。UHC達成のためには、国内避難民を含めたSRHサービス拡大が大切であると強調しました。また保守的な考えがあるため、SFPAは保健省や教員に早い段階で説明して協働で取り組んでいるという活動の工夫も説明しました。 ファミリー・ヘルス・オプションズ・ケニア(FHOK)事務局長エドワード・マリエンガ氏は、FHOKは、米国などドナー協力を得て、若者へのサービス、妊産婦死亡率削減、施設での分娩や避妊実行率を上げる取り組みに成果を上げてきたものの、資金が減らされている現状を説明。若者のためには避妊具の提供や、妊娠・出産した学生が偏見を受けないよう啓発を含めたユースフレンドリーサービスが大切だと訴えました。 最後に日本の若者を代表し、Japan Youth Platform for Sustainability代表・唐木まりも氏は、日本で女性が考える「美」には、社会の美の意識の刷り込みがあることから、既存のジェンダー意識にとらわれない女性の健康と、避妊を含めて女性の主体的な選択、女性がNOと言いやすい環境を社会全体で作っていく必要性があることを訴えました。 ※こちらの記事は、ジョイセフのウェブサイトに掲載されたものを、許可を得て転載しています。
Vision 2020 ジェンダーレポート
IPPF VISION2020 ジェンダーレポート ジェンダーの平等と女性のエンパワーメントを目指して 女性のエンパワーメントやジェンダーの平等には、セクシュアル/リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)の実現が不可欠です。女性が健康で、自分の健康や幸福、性に関する選択ができる社会でなければ、少女や女性が、妊娠・出産で命を落とす危険や、暴力に脅えることなく、教育を受けたり、活躍したりすることが望めないからです。この冊子では、女性が社会、経済、政治の場面で活躍するために必要な SRHRの実現について考えます。

IPPF事務局長の声明:米国政府のUNFPAへの資金援助停止に対するIPPFの見解
米国政府による国連人口基金(UNFPA)向け拠出金の停止に関する発表を受け、「(この決定は)世界中の女性や少女たちにとって絶望的な結果をもたらすだろう」と、国際家族計画連盟(IPPF)事務局長であるテウォドロス・メレッセは述べました。 メレッセ事務局長の発言は以下の通りです。 「米国政府が援助打ち切ろうとしている資金は、世界でもっとも貧困で、もっとも脆弱な立場にある女性や少女たちのヘルスケアのために使われるはずでした」 「それは避妊、妊産婦ケア、安全な出産をサポートするためだけではなく、ジェンダーに基づく暴力を防ぐためのプログラムにも使われるはずの資金でした」 「IPPFはUNFPAと緊密に連携して、世界中でこうしたケアを提供するのがもっとも困難な状況の中で活動してきました。特に、世界でもっとも貧困な国における、もっとも貧しい地域で活動をしてきました。このような環境に生きる女性や少女たちは特に脆弱な状況にあるため、この資金の打ち切りは、彼女たちに悲惨な 結果をもたらすでしょう」 メレッセ事務局長はさらに、「新しく発足した米国政権による、世界中の女性や少女たちのヘルスケアに対する、今年2回目の打撃です」と加えました。 「グローバル・ギャグ・ルール(メキシコシティ政策)の再導入により、既にIPPFや他の保健医療機関向けの米国の資金援助が打ち切りとなり、避妊サービス、HIVプログラム、ジカ熱の集団感染対策などの活動ができなくなってしまいました」 「(今回の政策によって)IPPFが失う見込みの1億米ドルの資金があれば、2万件の妊産婦死亡を防止できるはずです。また、この資金カットにより480万件の意図しない妊娠、170万件の安全でない中絶が起きる可能性があります」 「一つ、明確にしたいことがあります。米国政府によって打ち切られつつある拠出金は、いずれも中絶の実施や、強制的な生殖に関する政策の助長に費やされるものではありません。これは、(リプロダクティブ・ヘルスにかこつけた理由付けは)資金カットのための隠れみのでしかありません」 「権利に基づいて行動する組織として、IPPFはUNPFAをはじめとする保健医療機関や人権団体と協力し、何千万という女性と少女たちに対し、避妊法をいつ、どのように使うかを選ぶ権利を守り、命に関わるヘルスサービスへのアクセスを保障します」 「UNFPAは各国政府に働きかけ、持続可能な開発目標(SDGs)など、世界共通で合意した政策において協力するように求めています。グローバルな目標の達成は、すべての人々のセクシュアル/リプロダクティブ・ヘルスを守るためにも絶対に必要なことです」 「米国で政権が発足してから3カ月のうちに、重要な保健サービスを、もっとも必要としている人々に届けるための努力が2度も否定されたこときわめて遺憾に思います。この政治的決断によって、何万人もの命が失われることでしょう」

日本政府による拠出に関する発表を受けたIPPFからの発表
日本政府による拠出に関する発表(2017年3月28日付)*を受け、テウォドロス・メレッセIPPF事務局長から以下のコメントを発表します。 日本政府によるIPPFとUNFPAを通じた性と生殖に関する健康と権利(セクシュアル・リプロダクティブヘルス/ライツ:SRHR)への支援の継続に感謝します。米政府資金の大幅減など、世界のSRHRが苦境にある中、日本政府によるこの分野への継続的コミットメントの意思表明を特に歓迎します。 IPPFは、日本政府による長年にわたるIPPFへの支援に感謝します。また、IPPFが目前に差し迫った活動資金の危機を乗り越え、多くの人々(特に女性と少女)の健康と命を守るために、さらなる支援を期待します。 「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」の実現のためには,性と生殖に関する健康と権利に関するサービスの提供が必須であることをここに再度強調します。さらに、そのことがG7伊勢志摩サミット最終成果文書のみならず、国際女性会議WAW!(WAW!2016)最終成果文書、第3回国連防災会議成果文書、第6回アフリカ開発会議(TICADVI)成果文書でも明示されています。これらを可能とした日本政府による世界のUHC実現に向けたリーダーシップに敬意を表し、今後とも日本政府と緊密に連携し、世界の女性の健康と命を守り、持続可能な開発目標(SDGs)という共通の目標を達成するための努力を重ねることを約束します。 * 「国連人口基金及び国際家族計画連盟に対する拠出」(2017年3月28日付プレスリリース)はこちらをご参照ください。

IPPF 日本HIV/リプロダクティブ・ヘルス信託基金(日本信託基金、JTF)
2000年に、日本政府との協力によりアフリカとアジアのIPPF加盟協会が、包括的なHIVおよびセクシュアル/リプロダクティブ・ヘルスサービスを提供する活動を支援する先験的な協働プログラム「IPPF日本信託基金」が始まりました。 以後、このプログラムは、社会的弱者の生活に違いを生み出しただけでなく、IPPFのHIV関連事業の拡大にも大きな貢献をしてきました。 日本信託基金(JTF)プログラムが開始された2000年には、世界のIPPF加盟協会が提供したHIV関連サービス数は15万5,562件でしたが、2010年には、1,200万件にまで増大しました。
Pagination
- Page 1
- Next page







